
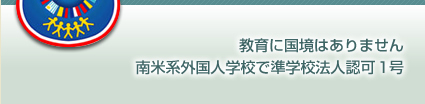

《10月》 松本雅美(ムンド デ アレグリア学校創立者で現校長)が 在東京ペルー総領事館主催教育フォーラムでのボランティアを ペルー領事より要請されスタッフとなる。 |
当時、松本雅美は子育て中の主婦であり横浜在住。 教育フォーラムの目的は、在日ペルー人子弟の教育の必要性を説くもの。 2~3年滞在の予定で子供連れで出稼ぎに来ていた人々の中には、学齢期の 子弟を教育の場へ向かわせず家庭に放置する例が少なからず見られた。親が 子供を学校に行かせない背景には、日本にはペルー人学校がほとんどなかった 事、日本の学校へは日本語が分からないため入っても適応できない事がある。 そこから、ペルーに帰国後、学校に戻った子供達に問題発生。日本での長い ブランクのため勉強についていけず留年者続出等。そのためペルー本国の 教師達がペルー教育省に日本での教育の改善を訴えたからである。 |
《11月》 |
東京都町田市と静岡県浜松市(いずれもペルー人集住都市)で ペルー総領事主催教育フォーラム開催 |
松本雅美は、1990年の「入管法」の改正で日系人労働者が大量に入国した 1990年代スズキ(株)人事部採用課で日系人採用係として勤務した経歴をもつ。 何かと頼りにされ日系人の「よろず相談窓口」の役も務め、彼らの家族を含めた 世話に奔走する。このフォーラムで再会したペルー人達に、フォーラム後、子供達 の窮状を訴えられる。それは、「日本の学校へ入ったが日本語がわからないため 授業が全く理解できない。 授業中はじっと座っているだけでつらい」 「日本の学校でいつも一人ぼっち」「いじめられて学校に行けなくなった」 「子供が勉強したがっているが道がない」 「家に閉じこもり精神的におかしくなった」「円形脱毛症になり笑わなくなった」 「学校さえあれば親戚に預けてきた子供を呼び寄せ一緒に暮らしたい」ほか、 後から後から噴出してくる。 そして言われる。 「マサミ、このままでは子供がかわいそうだ。安心して通える学校がほしい」 「お願いだ。子供達のために学校を創ってくれ」。 |
直ちに浜松市で市場調査開始。学校創設に向けて踏み出す。 |
「目の前に困って助けを求めている子供がいたからである。彼らは、たまたま ブラジル国籍やペルー国籍であったが、私にとって国籍はどこであろうと、あまり 問題ではなかった。ただ大人として、自分が受けてきた教育の恩恵を目の前の 子供達にも、という思い。学校に通う楽しさ、友達とふれあい勉強する楽しさを 体感してほしいという思いが強かっただけ」と当時の思いを後に記す。 (行路社『地球時代の多文化共生の諸相』より) |
《12月》 |
校舎賃貸契約締結 |
松本の私費を投じ、連帯保証人には遠方の母親を説得。 |
校舎探しは難航。「外国人お断り」の壁に遭遇し断られること数知れず。 その後、知人の紹介でようやく卸団地に辿り着く。卸団地組合に「校長が 日本人であること」により承諾を得る。 |
学校名を「ムンド デ アレグリア」に決定 |
「ムンド デ アレグリア」はスペイン語で「歓びの世界」という意味。 「学ぶ歓びを知り、友達と一緒に勉強する楽しさを存分に味わってほしい」 との思いを学校名に込める。 |