
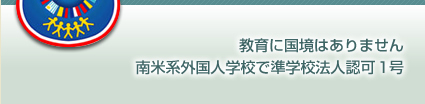

学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校
倫理規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校(以下「当法人」という。)の役職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、公共的性格を有するその職務の執行が公正に行われることを担保し、もって当法人に対する社会の信頼を確保することを目的とする。
(基本的人権の尊重)
第2条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。
(倫理監督者)
第3条 役職員の職務に係る倫理の保持を図るため、当法人に倫理監督者を置く。
第4条 倫理監督者は、当法人の役員の中から選任する。
(当法人の責務)
第5条 当法人は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 役職員がこの規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、直ちに調査を開始し、その結果、違反があったと認められるときには、厳正に対処すること。
(3) 役職員が、この規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により、役職員の倫理感の保持に努めること。
(倫理監督者の責務等)
第6条 倫理監督者は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 役職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 役職員と事業者等との関係が社会の疑惑や不信を招くようなものでないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、役職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
2 倫理監督者は、その職務の一部を役職員に行わせることができる。
(倫理行動規準)
第7条 役職員は、当法人の役職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 役職員は、他者に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 役職員は、常にその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 役職員は、その権限の行使に当たって、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の行為をしてはならないこと。
(4) 役職員は、勤務時間外においても、自らの行動が当法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(5) 役職員は、職務の遂行に当たって不正・不祥事等を知った時は、直ちに管理監督者(役員にあっては倫理監督者)に報告し、管理監督者は、隠蔽することなく顕在化させ、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第8条 当法人は、当法人の役職員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 当法人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当法人は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続をしないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4 当法人は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。
(倫理監督者への相談)
第9条 役職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、又は利害関係者との間で行う行為が次条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。
第2章 利害関係者との間において禁止される行為
(禁止行為)
第10条 役職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀又は香典その他
これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無
利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付
けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けるこ
と。
(5) 利害関係者から公開株式を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者に本来自らが負担すべき債務を負担させること。
2 前項の規定にかかわらず、役職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのも
のの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形
式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品
を使用すること。
(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供
を受けること。
(5) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受
け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(6) 本法人が推奨する研修において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け
又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
(7) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務とし
て出席した会議その他打合せのための会合の際における利害関係者との飲食
が、簡素な飲食とはいえず、かつ夜間におけるものである場合には、倫理監
督者が、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないも
のに限る。
3 役職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若し
くは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それら
の対価として役職員が支払った額が社会通念に照らして相当でないときは、第1
項第1号の贈与があったものとみなす。
(講演等に関する規制)
第11条 役職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(以下「講演等」という。)をしようとする場合は、職務の種類及び内容からみて、公正な職務の執行に対する社会の疑惑や不信を招く恐れのないようにしなければならない。
第3章 利害関係者以外の者との間において禁止される行為
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第12条 役職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
第4章 会計事務処理及び実効性の確保
(適正な事務処理の確保)
第13条 役職員は、規程その他法令等に基づき適正に事務処理がなされているかどうか、常に点検を行い、不適正な事務執行の未然防止に努めなければならない。
2 管理監督者は、会計事務処理が常に適正に行われるよう、役職員を指導監督する
とともに、必要な措置を講じなければならない。
3 次の各号の職務を行う場合は、それぞれ区分に応じて掲げる方策を講じるものと
する。
(1) 会計を行う職務
ア 役職員は、会計事務処理に当たっては、適正かつ効率的に行われているか、常
に点検を行う。
イ 役職員は、不正や事故を防止するため、口座振替の方法を探るなど、現金を取
り扱う機会を少なくするよう努める。また、管理監督者は、事務処理に当たっ
ては、複数の担当者を置くなどチェック体制を確保する。
(2) 現金等を取扱う職務
ア 役職員は、現金等は必ず金庫等で保管するとともに、現金の保管期間を短くし、
保管する必要がない現金は速やかに金融機関への入金等、適切な処理を行う。
イ 管理監督者は、現金を取扱う際は複数の役職員で行わせるなどチェック体制を
確保するとともに、金庫等の取扱者を限定し、定期的に金額等の点検を行う。
(3) 事業者等と癒着の起こりやすい職務
ア 役職員は、事業者等との契約については、適正な契約金額かどうか常に点検を
行う。
イ 管理監督者は、事業者等の選定に当たっては、公平性を確保するため、より具
体的な基準を設けるとともに厳正な審査を行う。
ウ 管理監督者は、同一役職員が契約事務と検査事務を処理しないように、事務処
理を工夫する。
(実効性の確保)
第14条 役職員は、本規程の遵守状況について自己点検を行い、倫理意識の向上に努めなければならない。また、管理監督者は、役職員に対し、機会のあるごとに倫理の保持に関する意識啓発を行うとともに、自らの行動が当法人の信用に影響を及ぼすことを、役職員一人ひとりに自覚させるよう努めなければならない。
2 管理監督者をはじめ教職員は、自らの職務と責任を自覚し、非行や犯罪のない職場
環境を形成するよう努めなければならない。
3 長期にわたって同一事務に従事することや特定の役職員に権限が集中することは、
不適正な事務執行につながる恐れがあるので、管理監督者は、役職員の業務分担の定
期的な変更や特定の役職員への権限の集中の防止に努めなければならない。
4 倫理監督者は、相談、届出若しくは報告があった場合又は役職員から本規程に関し
て相談等を受けた場合は、必要な指導及び助言を行う。
5 管理監督者は、役職員の倫理の保持に関し、役職員に対し必要な指導及び助言を行
う。
6 倫理監督者は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に別表「利益相反に該
当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を
講じなければならない。
第5章 管理監督者の地位にある者の情報開示及び説明責任
(贈与等の情報開示及び説明責任)
第15条 倫理監督者は、役職員が利害関係者と共に飲食をする場合は、必要に応じて、その内容について情報開示及び説明を求めることができる。
2 倫理監督者は、管理監督者の地位にある役職員が、事業者等から、金銭、物品その
他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又
は事業者等と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬の支払
を受けたときは、必要に応じて、その内容について情報開示及び説明を求めることが
できる。
(報酬)
第16条 前条いう報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、役職
員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって役職員が行う
ものであることを明らかにして行うものの報酬
2 前項第2号の報酬には、教員が自己の教育研究成果に基づいて行う講演等に係る報
酬を含まないものとする。
第6章 個人情報の保護
(個人情報の取扱い)
第17条 当法人が保有する個人情報の取扱いに関し、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)及び関係法令を遵守し、その収集、保管、利用に関する必要事項を定めるとともに、個人情報の開示、訂正、削除、及び利用等の中止を求める権利を明らかにすることにより、当法人の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に資する。
(定義)
第18条 前条にいう「個人情報」とは、次に掲げる者(但し、生存する者に限る。)に 関係する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別できるもの、又は、個人識別符号(その定義は個人情報の保護に関する法律第2条第2項による。)が含まれるもののうち、当法人が業務上取得または作成した全ての情報をいう。
(1) 当法人に在籍する学生、生徒、科目等履修生
(2) 当法人に在籍したことのある者
(3) 当法人への入学志願者及び出願者
(4) 第1号から第3号に掲げる学生等の保証人、保護者及び家族または親族
(5) 当法人が雇用しているまたは雇用していた教職員
(6) 当法人の役員等(理事・評議員・監事)
(7) 第5号から第6号に掲げる者の家族または親族
(8) 役職員の採用応募者
(9) 当法人が開催する公開講座、講演会、その他催し物の参加希望者及び参加者 (10) 当法人に寄付または寄贈した者
(11) 当法人の施設設備等を利用する者
(12) 第1号から第11号以外で、当法人に対して、照会、問合わせ、意見、質問、
要求、 要望等を行った者
(取得の制限及び方法)
第19条 当法人は、個人情報の取得に当たっては、当法人の教育・研究及び業務に必要な範囲内で利用目的をできる限り特定するとともに、その目的達成に必要最低限度の範囲で、個人情報の取扱いを行わなければならない。
(利用目的等の通知等)
第20条 当法人は、個人情報を取得するときは、あらかじめ当該本人に対し、その利用目的、用途、保有期間を通知し、又は公表するものとする。
2 前項にかかわらず、次の各号に定めるときは除外する。
(1) 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、当該本人または第三者の生命、身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 出版、報道等により当該個人情報がすでに公にされているとき。
(4) 法令の規程に基づくとき、または司法手続き上必要なとき。
(5) 当法人の権利または正当な利益を害するおそれがあると認めたとき。
3 当法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通
知し、又は公表しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第21条 個人情報は利用目的以外の目的に利用、または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
(1) 法令の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
2 前項により利用目的以外の目的のために個人情報を利用し、または提供するとき
は、対象とする個人情報の範囲をできる限り特定するものとし、個人情報のう
ち必要な事項に限定して利用、または提供しなければならない。
(第三者提供の制限)
第22条 当法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意
を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は学生・生徒の健全な育成の推進のために特に必要がある場
合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正管理)
第23条 管理者は、個人情報の安全保護及び正確性の維持のため、次の各号に掲げる事項について、適正な措置を講じなければならない。
(1) 紛失、毀損、破壊その他の事故の防止。
(2) 改竄及び漏洩の防止。
(3) 個人情報の正確性及び最新性の維持。
(4) 不要となった個人情報の破棄または消去。
(学外への持ち出し制限)
第24条 個人情報は原則として学外へ持ち出してはならない。ただし、個人情報を使用する業務を学外に委託するときは、この限りではない。
2 前項の業務委託を行う場合、管理者は、委託業者との間で個人情報の保護に関す
る覚書を締結しなければならない。
3 第1項の定めにかかわらず、教職員が持出す必要のある学生・生徒の個人情報に
ついては、管理統括者の命令もしくは許可により、学外持出制限の適用外とする。
その際、取扱い者は責任を持ってこれを取り扱わなければならない。
附 則
この規程は、2022年5月25日から施行する。